
帰化申請 日本語テストの注意点
そもそも国籍法において、帰化の条件に日本語の能力について明記された条文はありません。
「だったらなんでテストするの?」と怒り心頭の方もいるかと思いますが、これは目出度く日本人となった暁に「まるっきり、読み書きできません」では生活していくうえで不便でしょう、といういわば親心からの制度なのです。
したがって、決して高いレベルの日本語能力を求められるわけではなく、生活に困らない程度で十分とされています。具体的にはJLTPでN4~N3(小学3年生)レベルでOKです。
ただし「えっ、小学3年生?だったら余裕でしょ」などと甘く見ていると危険です。
危険な理由はズバリ「書くこと」です。
日本語の特色の1つとして、母音の数が少ない点が挙げられます。このために「話すこと」は比較的簡単な言語であるといえるでしょう。実際、帰化申請者はある程度長期間日本に在留していますので、皆さん日常会話程度なら問題なく「話せます」。
ところが、「話すこと」と「書くこと」は全く別物です。
実際のテストでは、「問題文を読んで、答えを書く」能力が問われてくるので、この場合例え流暢に話せたとしても関係ありません。外国人に限った話ではありませんが、仕事ではPC入力がメインで「紙にペンで書く」行為は年々少なくなっていますよね。普段ペンを持たない人が、いきなり試験の場でスラスラ書くことは難しいでしょう。苦手な方は漢字はともかくとして、ひらがな・カタカナは完璧に書けるように小学生用の練習帳などでシッカリ練習しましょう!
日本語能力テスト練習問題
練習課題1
ハッキリ区別できるレベルで書けるように練習しよう!
例:ひらがなの「い」と「り」いりぐち(入口)
例:カタカナの「シ」と「ツ」ホケンシツ(保健室)
練習課題2
ひらがなはカタカナに、カタカナはひらがなに直して書けるように練習しよう!
例:バスケットボールばすけっとぼーる
例:はんばーがーハンバーガー
例:おれんじじゅーすオレンジジュース
練習課題3
自分の身の回りのことを簡単な文章を書けるように練習しよう!
例:あなたの部屋にはどんなものがありますか?
例:あなたの好きな食べ物は?好きな理由も書いて下さい
例:あなたは昨日なにをしましたか?
例:あなたの友達はどのような人ですか?
日本語テストが行われるタイミングは「相談時」と「面談時」の2回あります。
冒頭に申し上げた通り、テストはするもしないも担当者次第なので、申請者によってテスト回数は0回・1回・2回・3回・4回・・・と様々です(不合格で再テストのケースもありえます。再テストの度に、審査期間がドンドン伸びてしまいます)
「相談時」のテストに合格しても安心はできません。「面談時」には別のテストが待ち構えている場合もあるからです。
ここまで、脅かすような事ばかり書いてきましたが、それには私なりの理由があります。
帰化申請は大変な労力をかけて膨大な書類を用意しなければなりません。
せっかく苦労して書類を全て揃えても「日本語能力」のせいで不許可になるのは、あまりにももったいなく、こんな残念なことはありません。このような事態は絶対に避けましょう!!というハマの行政書士からのメッセージ、理由はこれに尽きます。


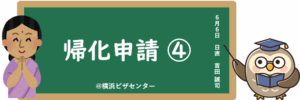
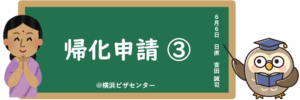
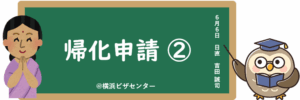
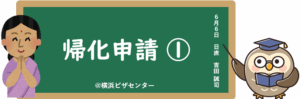
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] さて、以上が条文上の6要件なのですが、これ以外にも重要な要件として日本語能力要件があります。 帰化申請その5日本語テストに合格するためにでこの制度について詳しく紹介していますので、是非ご覧下さい。 […]