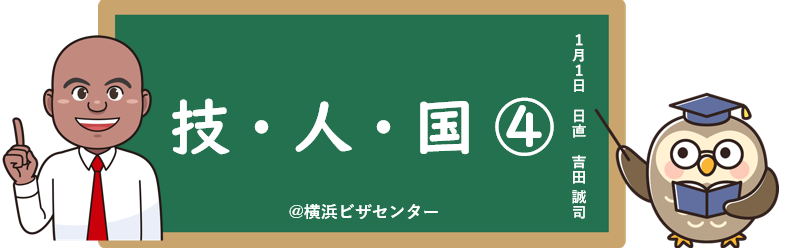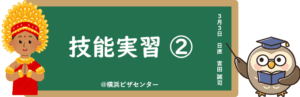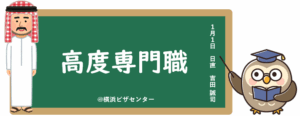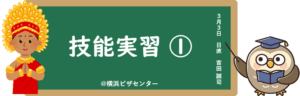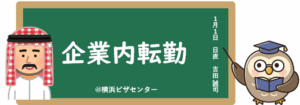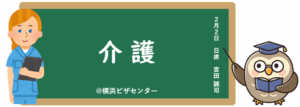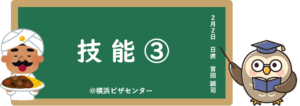考察1:技術・人文知識・国際業務の実務研修
まずは大原則として、
外国人が【技術・人文知識・国際業務】の在留資格で就労するためには、当該在留資格に該当する活動、すなわち、
学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務に従事することが必要です。
言い換えれば、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務以外はNGということです。
一方で、新人研修として実務研修期間を設けている企業も数多く存在するでしょう。
仮に、その実務研修で学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務以外の活動
(例えば、飲食店での接客や工場のライン業務など)を行った場合はどうなるのでしょうか?
入管はこの点を明確化すべく、HPでそれが日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって、在留期間中の活動を全体として捉えて、在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは、その相当性を判断した上で当該活動を「技術・人文知識・国際業務」内の活動であると認めています。
ただし、例えば雇用契約期間が3年間で契約更新も予定されていないような場合、その3年間のうち2年間を実務研修期間にあてる、といったような申請は認めない、としています。
要は、「雇用契約期間」と「実務研修期間」のバランスで判断するわけですね。
なお、「採用から1年間を超えて実務研修に従事するような申請については、研修計画の提出を求め、実務研修期間の合理性を審査する」
というルールもあります。

考察2:技術・人文知識・国際業務ビザでホテル・旅館等の宿泊施設業務
多くの外国人が利用する宿泊施設であれば、「通訳ができるスタッフが欲しい」と考える雇用主もいるでしょう。
通訳は【技術・人文知識・国際業務】の内、【国際業務】ですから当該在留資格で雇用することには何の問題もないように思えます。
しかしながら、宿泊施設には「宿泊客の荷物運版」「客室清掃」「料理の配膳・片付け」「駐車誘導」など様々な業務があり、本来の通訳業務に比べ、これらの業務に従事する割合が多い場合は注意が必要です。
考察1のケース同様に、「メイン業務」と「サブ業務」のバランスで判断するわけです。
実際の不許可事例を2つほどご紹介します。
①本国で経済学を専攻して大学を卒業した者が、本邦のホテルに採用されるとして申請があったが、従事する予定の業務に係る詳細な資料の提出を求めたところ、主たる業務が宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務であり、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となった。
②本国で日本語学を専攻して大学を卒業した者が、本邦の旅館において、外国人宿泊客の通訳業務を行うとして申請があったが、当該旅館の外国人宿泊客の大半が使用する言語は申請人の母国語と異なっており、申請人が母国語を用いて行う業務に十分な業務量があるとは認められないことから不許可となった。